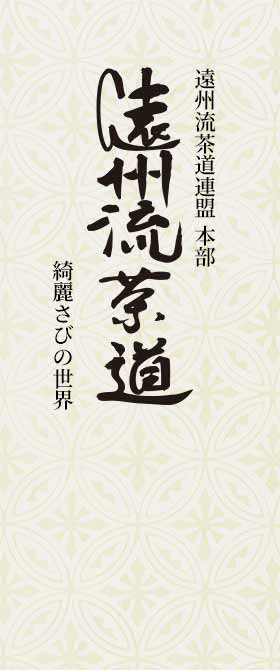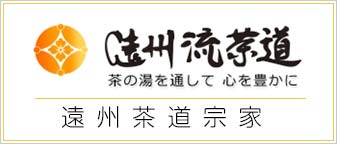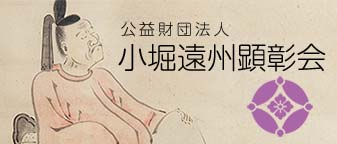日本の茶の起源
栄西から明恵へ
お茶が初めて日本に持ち込まれたのは遣唐使の時代。最澄は805年に比叡山の日吉大社に唐(中国)より持ち帰ったお茶の種を植えました。翌年の806年には、空海が唐から茶の種・石臼を持ち帰り、比叡山に植えたとされています。これらのお茶は、僧侶や貴族の間で薬用や儀式に用いられましたが、一般には普及せず、遣唐使が廃止されると次第に衰退していきました。

お茶を飲む習慣を日本に根付かせたのは、臨済宗の開祖である栄西禅師でした。鎌倉時代、宋(中国)からお茶の種子を持ち帰った栄西は、お茶の種類や効能、飲み方などを「喫茶養生記」に記すことでお茶の素晴らしさを伝えたのです。

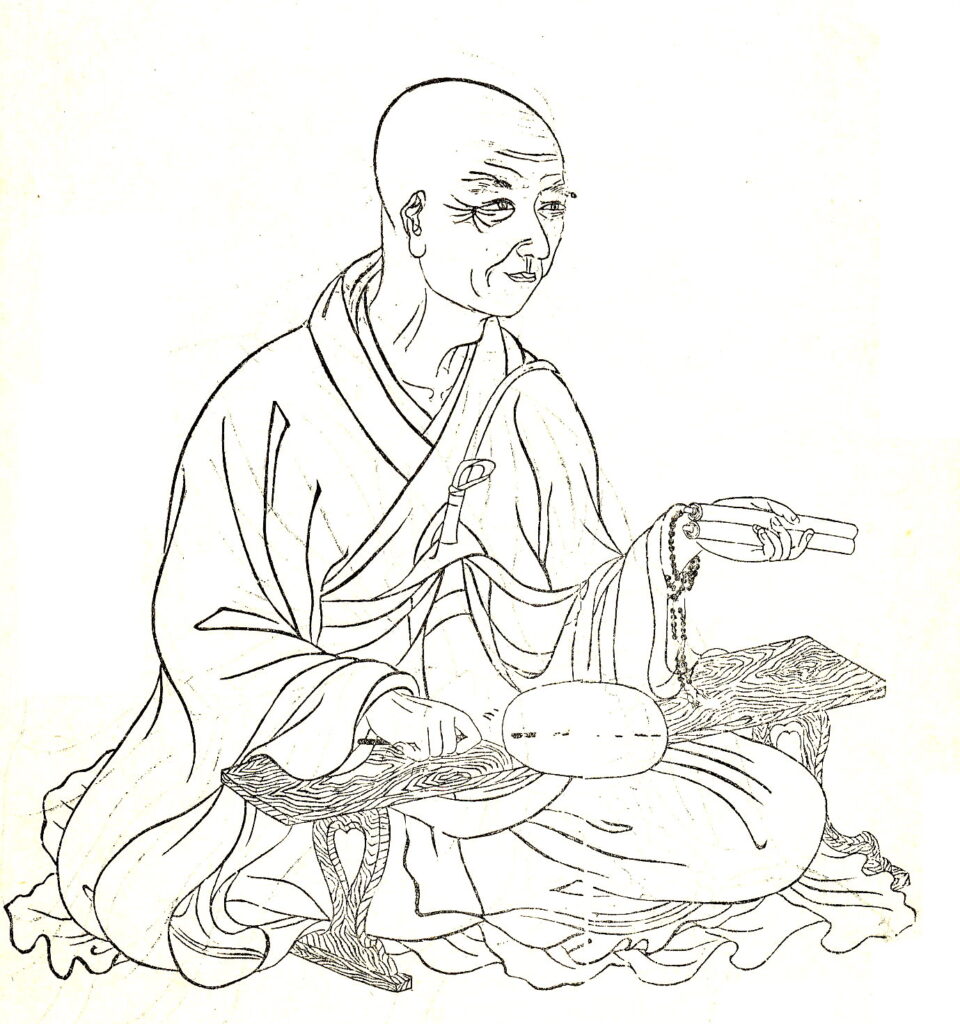
さらに、栄西から禅と抹茶の製法を引き継いだ明恵上人は、京都の栂尾にある高山寺や宇治にお茶の種子をまき、お茶が一般に普及する土壌を築きました。お茶が僧侶や武家に広まると、寺院で茶の湯の形式が整えられていく一方、 社交の場では、お茶の産地を当てる「闘茶」と呼ばれるゲームや、当時流行していた唐物(中国)の絵画・墨蹟・花瓶・香炉などを書院に飾り、それらを観賞しながら、お茶を飲んだり、和歌や連歌などを詠んだりする「会所の茶」が嗜まれました。
いつしかお茶は、人々の生活になくてはならないものとして深く浸透しました。

茶道の歴史