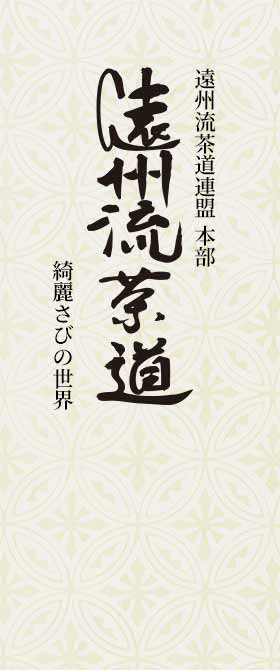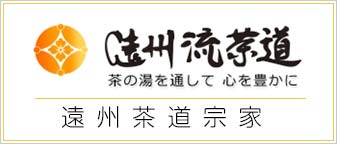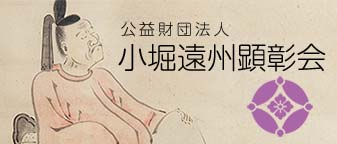二世 小堀正之(宗慶)

弱冠8歳、天皇の御前で揮毫
遠州46歳の時に嫡子となった小堀正之は、幼少の頃から遠州の茶友であった寛永の三筆の一人、松花堂昭乗に師事し、書を学んだ。あまりに能書であったことから、その評判を聞きつけた後水尾天皇が中宮御所に召して、弱冠8歳の時に天皇と東福門院の御前で揮毫するという栄誉に浴した。東福門院は後水尾天皇に嫁いだ徳川秀忠の娘、和子(まさこ)である。
神童と呼ばれた小堀正之は、茶の湯も12歳の時には、禅僧である江月和尚、天祐和尚の相伴として父遠州の茶会にも列席し、幼少の頃からその薫陶を受けていたと思われる。さらに17歳の時には遠州一世一代の舞台である将軍徳川家光への茶会で、給仕をつとめるなど茶の道を極めていった。
江戸在住の折には諸大名など迎える茶会を何度も開くなど、茶人としての評判は父譲りと人気があったと伝えられている。幕閣への参加を求められるも、遠州の強い希望もあり要職への就任を断った。遠州自身、伏見奉行や作事にも携わり、重い役職につくほど、交際費も膨大に腫れあがり、藩政に大きな負担を与えることを危惧していた、それ故、家を守るためにも、中央から離れた立場にいることを望んだからである。
近江孤篷庵を建立
遠州の死後、正之は将軍、諸大名、家臣、旧友たちに多くの茶道具を形見分けした。また、遠州のため地元小室に孤篷庵を建立した。京都の孤篷庵に対して、今では近江孤篷庵と称されている。55歳で亡くなり、下谷の廣徳寺(現在は練馬)に葬られた。この廣徳寺がのちに代々の墓地となっている。