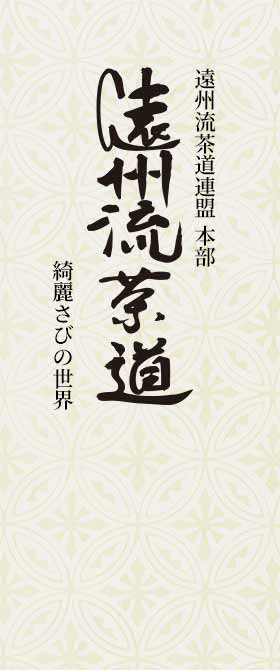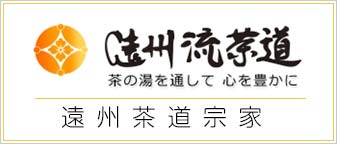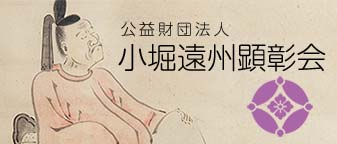十一世 小堀正徳(宗明)

門人や支援者らと流派を拡大
明治21年(1888)生まれた小堀正徳は、明治42年(1909)年、父十世小堀宗有が亡くなり22歳で十一世家元を継承した。東京美術学校で彫刻・塑像を習得し、また日本画も狩野探令に師事した。その人柄は温厚篤実で人々の信を一に集め、廣徳禅寺福富以清和向より、金剛経の「応無所住而生其心」の「其心」を庵号として贈られ、自らも一貫子と号した。
地方に出向き茶道教授
家元を継承した小堀宗明は遠州流の茶道教授方針や相伝の規則を定め、大久保北隠や式守蝸牛ら江戸千家の人々と茶道協会を設立した。これが現在の東京茶道会につながっている。明治神宮における献茶式も当時の有馬宮司より依嘱され、敬心会を発足、第一回の奉仕を行った。自身は青山に楽山祠(らくさんどう)、無習軒などの茶室を構え、茶道を教えた。また、地方に出向いても茶道を教授し、遠州流の拡大に力を注いだ。
益田鈍翁をはじめ大正茶人たちとの交流も厚く、宗明には多くの門人や支援者がいた。大正8年(1919)、高谷宗範が京都木幡に松殿山荘という広大な山荘を巨額の建設費をかけて建設、そこでの茶道大学を構想した。その山荘をすべて提供する条件で宗明を迎えようとしたが、小堀宗明は石黒忠悳と相談のうえその申し出を断り、東京で活動を続けることにしたという話も残っている。
昭和12年(1937)、石黒忠悳、三井泰山(永坂三井家)、近藤重彌、七海兵吉、吉川兵次郎らと泰和会を結成。後に団伊能、三井高大らも加わり、遠州流の発展に大きく寄与した。
戦争が激しくなると、国民の服装は男女とも厳しく規制されたが、茶道は特別に着物の着用が認められていた。だが、人目を憚ったのか、女性は茶会場までモンペを着用し、寄付でモンペを脱いで茶会に臨んだといわれている。