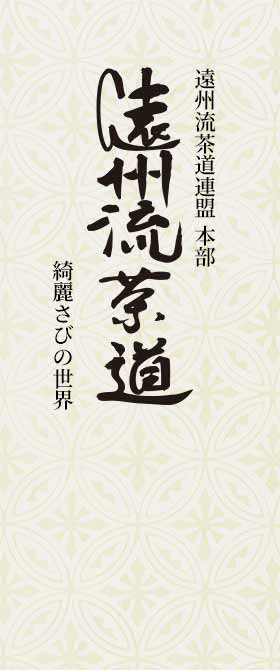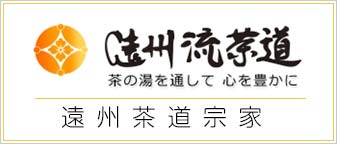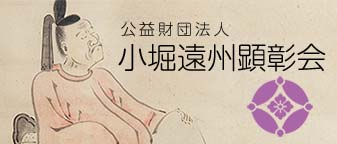小堀遠州

「綺麗さび」への道程 流祖小堀遠州の生涯
王朝時代の幽玄と中世の侘びとを融合させた新たな美意識、「綺麗さび」を確立することで、茶の湯の世界に大きな足跡を残した流祖、小堀遠州。大名茶人でもあった小堀遠州は、江戸幕府初期の有能な行政官であり、建築や造園の名手として多くの作品も残している。
織田信長が天下布武の拠点として、日本で初めて五層の天守閣を備えた安土城を、琵琶湖を望む安土山に築いた天正9年(1579)。同じ琵琶湖の北に位置する坂田郡小堀村(現在の長浜市小堀町)で一人の男の子が産声をあげた。後の小堀遠州である。幼名を作介、元服して正一(まさかず)と名乗った。
藤堂高虎の養女を正室に
父である新介正次は元々浅井家の家臣として仕えていた。しかし信長によって浅井家が滅ぼされると、その才覚を買われた正次は豊臣秀長の重臣となり、太閤検地など主に内政面を担当して活躍した。秀長亡き後は徳川家康に仕え、新介、作介親子はその出世とともに各地を巡ることになる。慶長2年(1597)小堀遠州19歳の時に、築城技術に長けた藤堂高虎の養女を正室に迎えたことは、後の小堀遠州に大きな影響を与えることになる。
関ヶ原の戦いの後、新介はその功により備中国のうち1万4460石(岡山県高梁市)を与えられ大名に列すると、備中国国奉行に任命されて、行政面から幕府を支えることになった。
しかし慶長9年(1604)、江戸に向かう旅の途中に藤沢にて病死する。65歳であった。

駿府城築城の功績で遠江守に
26歳で後を継いだ正一は、早速、後陽成院御所の作事を命ぜられる。その名を世間に知らしめたのは、駿府城の修築であった。慶長10年(1605)に三男・徳川秀忠へ征夷大将軍を譲った家康は、駿府に大御所として入府した。慶長13年(1608)、駿府城作事奉行に命じられた正一は、その功績によって諸太夫従五位下遠江守(しょだいふじゅごいのげとおとうみのかみ)の冠位を与えられた。小堀遠州の登場である。
当時大名は本名でなく冠位で呼び合うのが慣わしであり、遠江守となった正一は以降小堀遠州と呼ばれるようになった。元和5年(1619)41歳の時には、近江浅井郡へと所領替えとなり、小室(こむろ)藩主として、30年ぶりに故郷へ戻ることになった。ただ小堀遠州をはじめ歴代の小室藩の藩主は幕府の重要な役職に就いていたので、ほとんどこの地に居ることはなかった。
小堀遠州は名古屋城天守閣、大坂城天守閣、二条城、桂離宮、仙洞御所など日本を代表する城、御所の作事に携わった。さらに龍光院内密庵(みったん)席。孤篷庵、南禅寺方丈庭園、金地院鶴亀の庭など、数多くの建築、造園にも携わった。また、幕府の行政官として近江国奉行、河内国奉行、伏見奉行などの要職を歴任した。伏見奉行は生涯にわたってその任にあり、行政官としてもその手腕を発揮した。
伏見を舞台に茶人たちと交友
文禄2年(1593)15歳の小堀遠州は古田織部について茶の湯を習い始めた。同時期に春屋宗園禅師のもとに参禅をする。織部がその代名詞ともなる「へうげもの」の茶碗を使って世の茶人たちを驚かし、茶の湯の名人として世に知られるのは慶長4年(1599)その6年後になる。師のひょうげた茶碗を見た小堀遠州がどのように思ったのか、興味深いところである。この頃の京都・伏見には織部を中心に、小堀遠州はもちろん、上田宗箇(宗箇流の祖)、金森可重(宗和流の祖、金森宗和の父)、桑山元晴(石州流の祖、片桐石州の祖である宗仙の兄)など、武家茶人が集まった。利休亡き後、伏見を舞台に次代を担う茶人たちが交友したのだ。そして21歳となった小堀遠州は、初陣となる茶会をこの年に催した。
禅に傾倒、「大有」の道号を受ける
禅に傾倒した小堀遠州は、慶長14年(1609)遠州31歳の時に春屋禅師より「大有」の道号を受ける。慶長17年(1612)には、江月和尚を開基として孤篷庵を建立した。記録に残る生涯400回ほどの茶会の多くは、寛永期以降に開かれたものである。招かれた客は、延べ2000人にも及び、徳川将軍をはじめ僧侶、公家、大名、文化人、商人、町人、職人と、幅広い層にわたっている。
小堀遠州の茶の湯の特色は「綺麗さび」に集約される。「綺麗」という言葉は、優美で洗練され、装飾性に富んだ、江戸時代を象徴する美意識であった。その中心に小堀遠州がいたのである。
王朝文化、東山文化、さらには王朝時代の幽玄と中世の侘びとを融合させた新たな美意識が「綺麗さび」であり、武士の生き方でもあった。
掛物に和歌を、和物の茶入も
小堀遠州は禅の高僧による書の墨蹟が中心だった掛物に、和歌も用いるようになり、中国からの渡来品である唐物中心だった茶入の世界には、瀬戸茶入を中心に和物(日本製)の焼物を導入。本歌取りの手法を導入して茶入に歌銘を付与するなどして新たな価値を加え、後世に中興名物と称される茶道具の名物を選定した。各藩の大名たちは小堀遠州の指導を仰ぎ、各地の窯を指導、世に遠州好みと呼ばれる茶道具を数々送り出した。
寛永13年(1636)、58歳の時に、江戸品川御殿において三代将軍徳川家光に献茶。以来将軍家茶道指南役として、その名を不動のものとした。晩年の寛永19年(1642)から正保2年(1645)までの足掛け4年間は、特に「遠州の江戸詰」といわれ、家光が将軍家文化の興隆を望んでその膝下に在勤させたのである。4年の江戸詰を終える際、家光から立花丸壺の茶入を拝領した。正保4年(1647)2月6日、伏見奉行屋敷で死去。享年69歳。孤篷庵に葬られた。